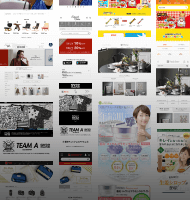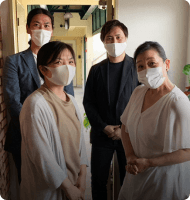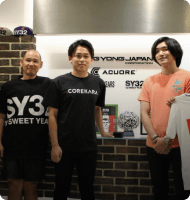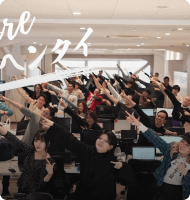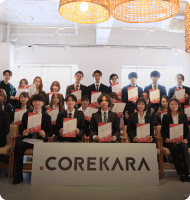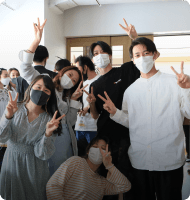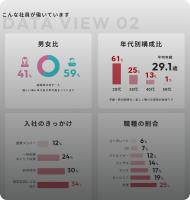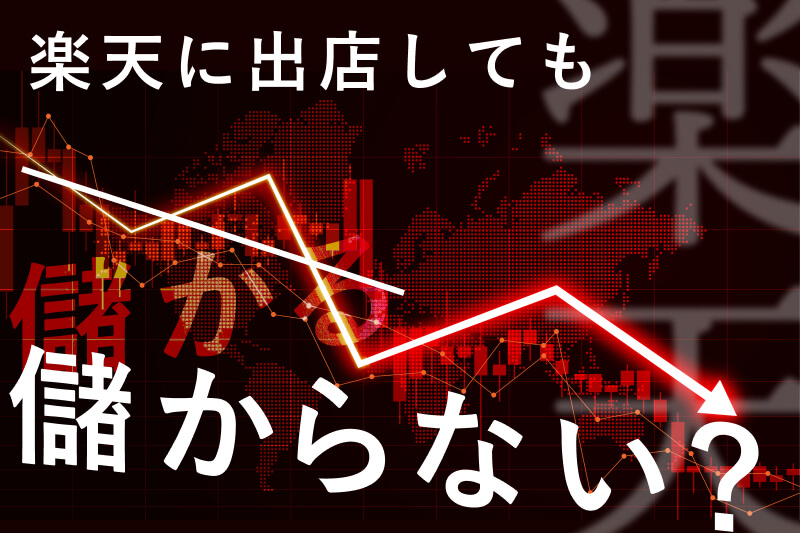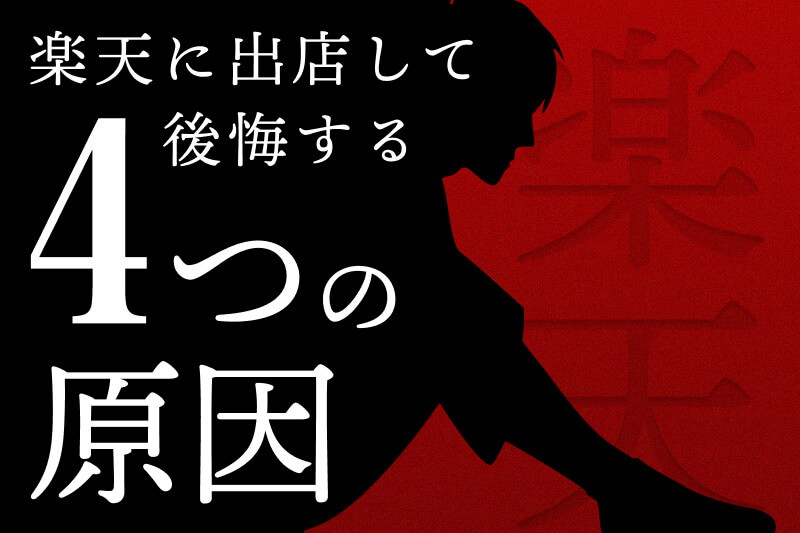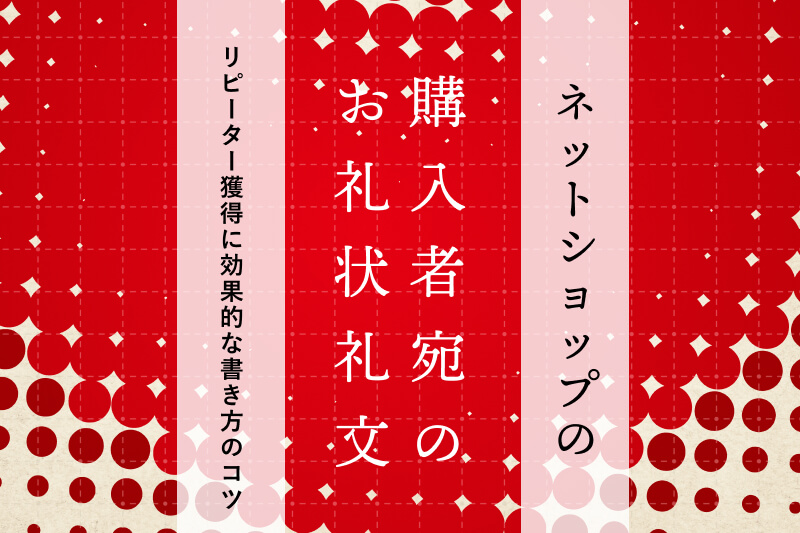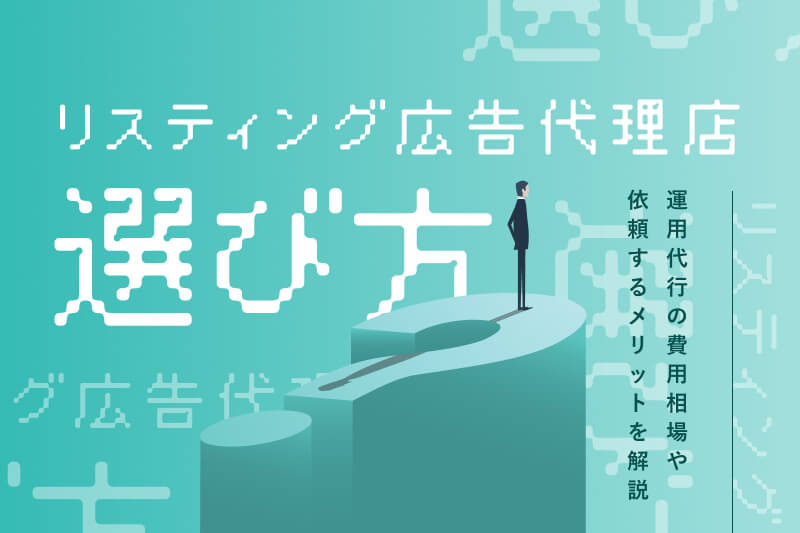冷凍食品を販売するための営業許可や資格|飲食店や通販での手続きを解説


株式会社これからの取締役。 2004年、IT系上場企業に新卒入社。ECサイトのコンサルティング営業に従事。 その後、株式会社これからに創業メンバーとして参画し、取締役就任。 小規模ショップから東証1部上場企業まで、500社以上のECサイト戦略について支援。 自社ECサイト支援で業界トップクラスの実績を誇る。 年間100回以上のECセミナー登壇や大規模展示会での講演多数。 書籍「図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)の執筆も手がける。
冷凍食品を販売するには、「食品衛生法に基づく営業許可」や「食品衛生責任者」の資格が必要です。
すでに食品の製造業で営業許可を取得している方でも、自身で製造した冷凍食品を販売するためには新たに申請が必要です。
必要な許可や資格の取得には、必要な設備を揃えたり、規定の手続きや講習会の参加が必要です。
この記事では冷凍食品の定義から、販売に必要な許可や届出を解説します。
冷凍食品の販売に必要な許可と届出一覧
すでに食品を扱っている事業を営んでいても、冷凍食品を新しく始める場合には、新たに「冷凍食品製造業」、または「複合型冷凍食品製造業」の営業許可が必要です。
冷凍食品製造業
- ・そうざい製造業にかかる食品を製造し、その食品の冷凍品を製造する営業。
- ・小売り販売用に包装された農水産物の冷凍品も含まれます。
- ・製造にあたっては冷凍食品の規格基準に適合する必要があります。
複合型冷凍食品製造業
- ・冷凍食品製造業と併せて食肉処理業・菓子製造業・水産製品製造業・麺類製造業にかかる食品の冷凍品の製造を行う営業
- ・HACCP※に基づく衛生管理を実施する場合に限ります。
※令和3年6月から、原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。あわせて、一般衛生管理や、HACCPによる「衛生管理計画書」を作成する必要があります。
参考:東京都福祉保健局
これらの許可を取るためには、「食品衛生法に基づく営業許可」に基づき、都道府県知事が定めた設備の基準もクリアする必要があります。
さらに、冷凍食品をどのように販売するかによって許可が変わるため個別で紹介します。
冷凍食品を自身で製造・販売する
冷凍食品を自身で製造して、販売する場合は以下の許可と資格が必要です。
| 手続き内容 | 必要な内容 | 費用 | 申請先 |
| 許可 | 冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業 |
25,200円 35,200円 ※1 |
所轄の保健所 ※2 |
| 資格 | 食品衛生責任者 | 12,000円 ※1 |
所轄の衛生協会 |
※1.掲載している許可や資格の費用は、東京都の費用をベースにしており、自治体によって異なります。
※1.営業許可の有効期間は5~8年ほどです。 正式な期間は自治体ごとに定められています。
※2厚生労働省のホームページにある「食品衛生申請等システム」でも申請可能
飲食店で冷凍食品を製造・販売する場合は、すでに飲食店の許可を得ていても、別途で冷凍食品の許可が必要です。
冷凍食品を小分けして販売する
既製品の冷凍食品を小分けにして容器包装に入れ、または容器包装して販売する場合、食品の小分け業の許可が必要です。
| 手続き内容 | 必要な内容 | 費用 | 申請先 |
| 許可 |
食品の小分け業 |
16,800円 |
所轄の保健所 |
| 資格 | 食品衛生責任者 | 12,000円 | 所轄の衛生協会 |
対象となるのは、以下に記載した食品(既製品)を小分けして容器包装に入れる、または容器包装で包むものです。ただし調理や小売販売における小分けは対象外です。
- ・菓子製造業
- ・乳製品製造業(固形物に限る。)
- ・食肉製品製造業
- ・水産製品製造業
- ・食用油脂製造業
- ・みそ又はしょうゆ製造業
- ・豆腐製造業
- ・納豆製造業
- ・麺類製造業
- ・そうざい製造業
- ・複合型そうざい製造業
- ・冷凍食品製造業
- ・複合型冷凍食品製造業
- ・漬物製造業
既製品の冷凍食品を販売する
既製品の販売だけの場合、営業許可は不要です。ただし、食品衛生法では販売業に区分されるため、平成30年6月の法改正により届出が必要です。
なお、冷凍食品をその場で調理すると許可が必要になるため注意が必要です。
| 手続き内容 | 必要な内容 | 費用 | 申請先 |
| 届出 | 営業届出 |
不要 |
所轄の保健所 |
届出が必要な詳細な販売区分は下記をご覧ください。
参考:大阪市の営業届出制度について
※当社2023年10月実績
営業許可に必要な基本的な条件
営業許可を得るには、食品衛生法で定められたいくつかの条件を満たす必要があります。
営業許可を取るのに必要な条件は以下のように分かれます。
- ・資格
- ・施設に関する共通する項目
- ・施設に関する業種ごとの項目
・資格
施設ごとに1人以上、食品衛生責任者が必要です。
・施設(共通基準)
施設の構造、設備、給水状況などが主な項目となります。
・業種(特定基準)
飲食店・菓子製造業など各業種ごとによって設けられている設備の基準です。
上記の基準は、各都道府県ごとで個別に定められています。事前に各都道府県の保健所に相談しましょう。
冷凍食品の定義
以下を満たす食品が冷凍食品とされています。
冷凍食品の安全性を確保するために食品衛生法で規格が定められています。規格に合わないものは、製造、販売などを行うことができません。
冷凍食品を製造するために、どんな作業や規格を満たす必要があるのか参考までにご紹介します。
・下処理
新鮮な原材料を洗浄するなど、あらかじめ下処理されていること。
・急速冷凍
組織が壊れて品質が変わらないよう、低温で急速に凍結されていること。
・品質保全のための包装
流通過程における汚染や乾燥、酸化から食品を守るために規定の仕様で包装されていること。
・保存温度
生産から販売まで一貫して、-15度以下(冷凍食品協会の自主的取扱基準では-18度以下)に保たれていること。
・分類
冷凍前の加熱調理の有無、摂取前の加熱調理の必要性で分類されています。
- 無加熱摂取冷凍食品(凍結前の加熱の有無にかかわらず、加熱せずにそのまま食べられるもの)
例:フローズンケーキ、果実類など - 生食用冷凍鮮魚介類(刺身などに用いられる冷凍された鮮魚介類)
例:魚介類の刺身やむき身など - 加熱後摂取冷凍食品(凍結前未加熱)(凍結前に未加熱、または一部加熱済であり、加熱をしてから食べるもの)
例:衣をつけたフライ類や焼く前の餃子など - 加熱後摂取冷凍食品(凍結前加熱済)(凍結前に加熱済であり、加熱をしてから食べるもの)
例:フライドポテトやウナギのかば焼きなど
・成分規格
食品衛生法により、製品として細菌数等の細かい基準が設定されています。基準を満たしていない冷凍食品は販売が禁止されています。
詳しくは下記をご覧ください。
神奈川県の食品衛生
※2023年3月28日 当社実績
まとめ
冷凍食品を販売するには、販売内容によって取得すべき許可や資格が異なります。
例えば、飲食店で冷凍食品を製造・販売する場合は、「飲食店営業」の許可を持っていても冷凍食品の許可が必要です。ただし、食品衛生責任者を新たに取得する必要はありません。
食品衛生責任者の取得は難しいものではありません。講習会に参加するだけです。
営業許可は営業施設基準に従い施設を整えれば取得できます。ただし、自宅での製造は難しいため、専用の施設が必要になることが多いでしょう。
商品を販売する前に、保健所に念のため相談することをおすすめします。
ネットで販売する場合にも、どのように販売するのかいくつかの方法があります。時期や案件によっては、ネットショップの構築に必要な資金を、国からの補助金で捻出できるかもしれません。
詳しいことは専門の会社に相談してみましょう。
※当社2023年10月実績
関連記事
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/14(金)