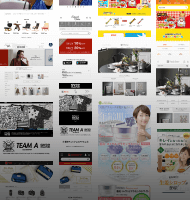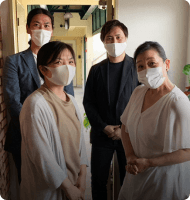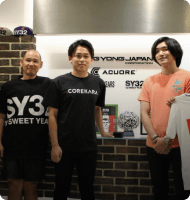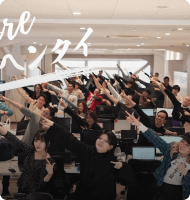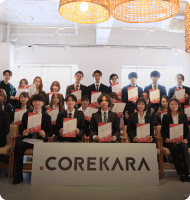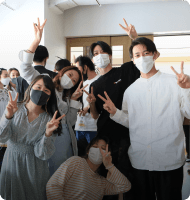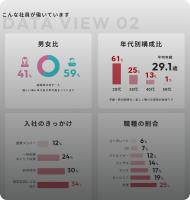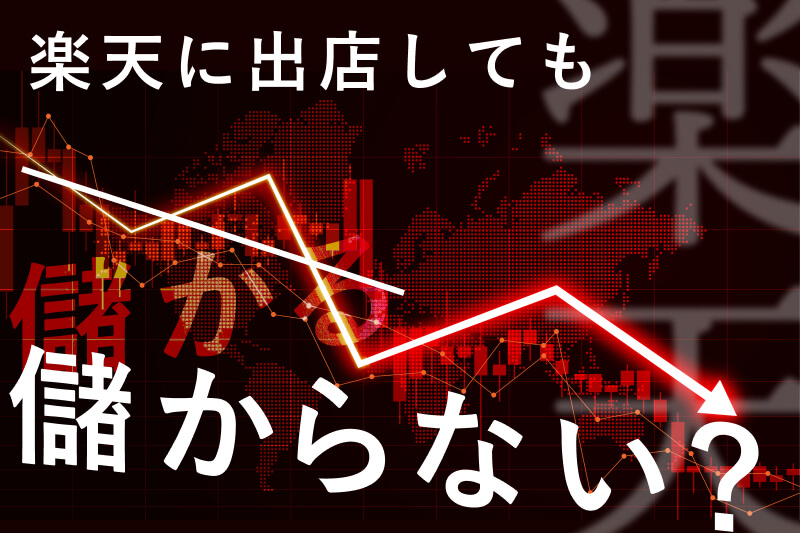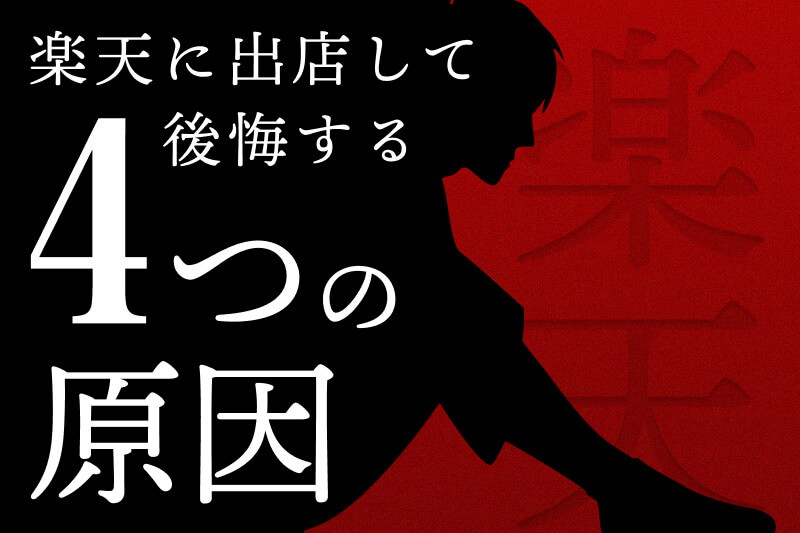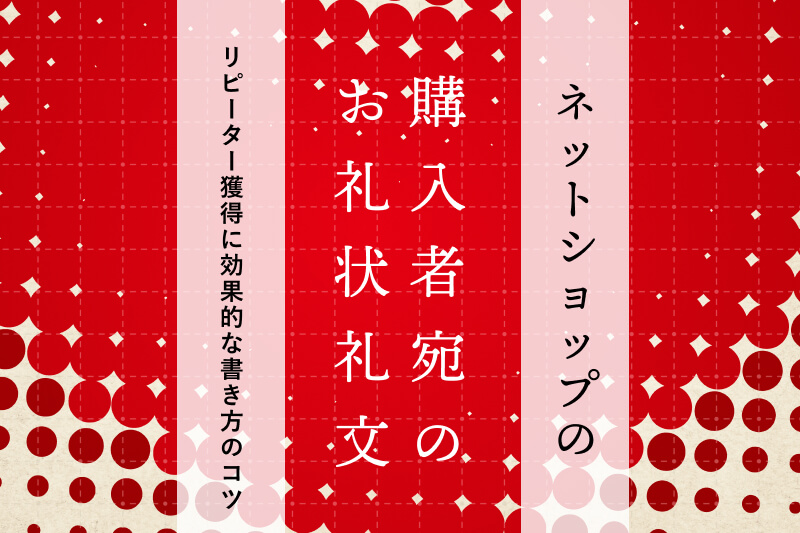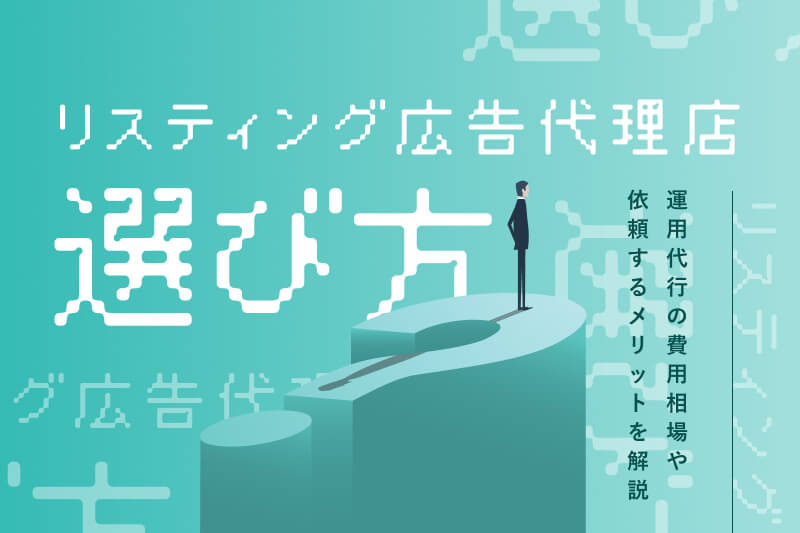食品ECサイトとは|課題や市場規模・EC化率から成功事例を解説

ネットサービスの普及が進み、さまざまな分野でEC化が進んでいるなかで、食品業界のEC化率は大きく後れをとっています。しかし、増加幅は小さいながらも食品業界でもEC化率は高まっています。そこでこの記事では、食品ECが抱える課題や現状、取り組むメリット、成功させるポイントを紹介します。
食品ECとは

食品ECとは、インターネット上で食品を販売し、自宅まで配送を行うネットショップやネット通販のことをいいます。その販売方法は大きくわけて3つあります。
| 種類 | 概要 |
| 一般的な食品ECサイト | 小売店やメーカーが開設した自社ECサイトや、ECモールに出店して開設したECサイトです。また、お取り寄せサイトなど、小売店を通さずに顧客に直接販売するECサイトもこれに該当します。 |
| ネットスーパー | イオンやイトーヨーカドーなどのスーパーがインターネット上に開設した食品を取り扱う自社ECサイトのことです。大型のスーパーによる展開が見られます。インターネット上で注文を受けた商品は、ユーザーの居住地の最寄りのスーパーから配送されます。 |
| サブスクリプション型の食品EC | 申し込まれたプランやコースの食品・食材を定額で定期的に届ける販売する方法です。オーガニック専門や野菜スープなど、特化型の食品によく用いられています。 |
食品ECの市場規模とEC化率
引用元:経済産業省「電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」
経済産業省が2023年に公開した調査結果によると、食品、飲料、酒類におけるEC化率は2021年には3.77%、2022年は4.16%と右肩上がりに成長しています。2022年に公開された同調査によると、2019年は2.89%だったところ、2020年には3.31%に上昇。新型コロナコロナウイルスの流行による外出自粛期間があった、2020年には増加率が特に上がりました。
他の多くの分野と比べると、食品関係の分野ではEC化率はかなり低いのが現状です。
ただし、食品ECの今後の成長には期待が集まっています。下記は食品ECの市場規模とEC化率の推移を表したグラフです。
上記のグラフからも分かるとおり、市場規模が拡大するのに伴い、EC化率も上昇しています。
少し話はずれますが、アメリカでも同じくコロナ禍を経て食品のEC化率が上昇。利便性に気づいたユーザーが継続利用することにより、さらなる成長が見込めると考えられています。日本でも同様に、食品ECの将来性は明るいと予測できます。
※当社2023年10月実績
食品ECの売上高ランキング

日本流通産業新聞が実施した「2021年版 食品通販売上高ランキング」によると、食品ECの売上高ランキングは以下のようになっています。
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 増減率(%) |
| 1 | Amazon(日本事業) | 60,000 | – |
| 2 | オイシックス・ラ・大地(Oisix) | 49,860 | 39.0 |
| 3 | イトーヨーカ堂 | 35,734 | ▲10.0 |
| 4 | 楽天グループ | 30,000 | – |
| 5 | ベルーナ | 26,614 | 42.9 |
参考:日本流通産業新聞「2021年版 食品通販売上高ランキング」
2021年時点では、コロナ禍需要による追い風が続いており、一般食品に加えてスイーツやミネラルウォーター、酒類や菓子などのEC売上が増加しました。
コロナ禍を機に食品ECの利用を開始したユーザーが、その高い利便性やライフスタイルに適したサービスに慣れて定着していくと考えられることから、食品EC市場の成長が期待されています。
食品業界でEC化が進まない理由
将来性が期待されている一方で、食品業界でのEC化率はまだまだ低いのが現状です。これには次のような理由が挙げられます。
- 生鮮食品との相性が悪い
- 実店舗の利便性が勝る
- 利益が出にくい
まず、食品は品質にバラツキが出やすいため、実物を見たいという人が多いほか、その日のメニューを思いつきで決めて食材を購入する人も多く、なかなかまとめ買いに繋がりにくいという側面があります。
また販売側にとっては、食品は単価が安く、単品買いでECサイトを利用されると利益が出にくいためEC化が進みにくいという理由もあります。
生鮮食品との相性が悪い
生鮮食品は鮮度が味に直結するため、実物を見て確認したいというニーズがあります。実店舗では実際に確認できますが、ECサイトでは不可能です。
そして家電や生活雑貨などと違って、サイトに掲載されている形や色、大きさの商品がそのまま届くとは限りません。
ユーザー側の「ハズレ商品を引きたくない」という心理も相まって、ECサイトでの購入率が上がらない(=需要が高まらない)ことが、EC化に歯止めをかけている要因の一つです。
実店舗の利便性が勝る
高齢者の増加に伴い買い物の移動距離が短くなったことや、競合店の増加による競争激化などを背景に、小商圏化が進行しています。
一般的には生活圏内に1つ以上スーパーやコンビニがあり、欲しいとき、すぐに生鮮食品を手に入れられる環境が整っていることがほとんどでしょう。
つまり食品においては手元に届くまで時間がかかるECサイトをわざわざ使う必要がなく、このことがEC化率を遅らせる原因になっています。
利益が出にくい
最後は販売者側の理由です。食品はEC化率の高い家電や生活雑貨、衣類などと比べて単価が安いという特徴があります。そのため、まとめ買いをする場合を除いて、客単価が低くなりやすいのです。
その一方で温度や保存方法、配送方法などには特別な配慮が必要で、ランニングコストは高くなります。こうした理由から、食品ECは利益を出しづらく、積極的に取り組む企業が少ないこともEC化率が進まない原因として挙げられます。
食品ECに取り組むメリット

EC化率が低い状況のなか、食品ECに取り組むメリットは次のとおりです。
- 商圏・販路の拡大を狙える
- 機会損失を低減できる
- ニッチな商品も取り扱える
- 詳細な商品情報・ストーリーを伝えられる
- 顧客の声を商品・サービスに反映させる仕組みがつくれる
以下で詳しく見ていきましょう。
商圏・販路の拡大を狙える
食品ECの最大のメリットは、商圏・販路の拡大にあります。少子高齢化による人口減少に伴い、地方などエリアによっては商圏人口も減少しています。一般的に商圏人口が減少すると、売上も減少します。この状況を打破できるのが、EC化というわけです。
実店舗では、店舗周辺の狭い商圏でしか販路を見いだせませんが、ECサイトであればインターネットが繋がる全国各地にまで商圏・販路の拡大が可能です。リーチ数が増えることで、売上アップにも期待が持てます。
機会損失を低減できる
実店舗では閉店時間があり、お盆やお正月などは休業するお店もあります。当然ですが、お店が閉まっている間は買い物ができません。
その点、ECサイトは24時間365日オープンしており、いつでも買い物できます。時間を問わず在庫の確認もできるため、実店舗で起こりうる販売機会の損失を低減できます。
ニッチな商品も取り扱える
実店舗では商品を陳列できるスペースに限りがありますが、ECサイトの場合はほぼ無限に商品を掲載できます。そのため、実店舗では取扱いが難しい「需要は少ないけど利幅が大きいニッチな商品」でも取扱いが可能になります。
需要が少ない商品はECサイトでも売れないのではないかと思われるかもしれません。ですが、「ECサイトならあるかもしれない」と希望を持ち、検索するユーザーは一定数います。その際に、実店舗では見つからない商品を取り扱っていることが分かれば、一部のユーザーからはありがたい存在として重宝されることになるでしょう。
詳細な商品情報・ストーリーを伝えられる
実店舗では所狭しと商品が並べられているため、生産者情報や商品ができるまでのストーリーを余すことなく伝えることはできません。
その点、ECサイトでは1商品につき1ページを用意できるので、商品の詳細情報や生産・開発に至ったストーリーを通して各商品の魅力を存分に伝えられます。
顧客の声を商品・サービスに反映させる仕組みがつくれる
実店舗でもアンケート用紙が設置されていることがありますが、わざわざ足を止めて回答する人は多くありません。
一方、ECサイトの場合は、注文のついでにアンケートへの回答に協力を仰ぐことも可能です。アンケート結果も集計しやすいので、実店舗よりも容易に顧客の声を商品・サービスに反映させる仕組みの構築ができます。
※当社2023年10月実績
食品ECを成功させるためのポイント

食品ECを成功させるためには、次のようなポイントを抑える必要があります。
- 試しやすいサービス・商品を用意する
- 独自性のある商品ラインナップを提供する
- 利便性・操作性の高いサイトを構築する
- 定期購入・サブスクリプションを導入する
- 集客方法を検討する
- 物流拠点・システムを整える
簡単にいうと、ユーザーが買いやすい環境を整えることです。また、冷凍食品やお米など、自分で買ってもECサイトで購入しても品質に差がでないうえに、運んできてもらえるという利便性が勝る商品を取り揃えるのも、EC化成功のポイントとして挙げられます。
試しやすいサービス・商品を用意する
食品の購入は実店舗で充分と思っている人に対してECサイトでの購入を促すには、「試してみようかな」と思える以下のような動機づけが必要です。
- お試しセット
- 初回限定 送料無料
- 〇〇〇円以上購入で、おまけプレゼント
- ECサイトを利用するとポイント3倍
これらの施策によって、一度試してもらうことで、「おいしい」「便利」と思ってもらえれば成功です。商品の質や利便性が高いことを分かってもらえれば、継続利用につながり、売上アップにも期待が持てるようになります。
独自性のある商品ラインナップを提供する
実店舗にはない独自性のある商品ラインナップを提供するのも、ECサイトの利用を促進するうえで有効な施策です。たとえば、次のような施策により独自性を打ち出せます。
- 無添加・無農薬にこだわった安全性の高い食材
- 地域の特産品
- 季節限定商品
- SNSで話題の商品
- お歳暮・お中元などの贈り物用のセット商品
特にお歳暮やお中元をはじめとした各種贈り物商品は、売上が大きく伸びやすい傾向にあります。
また、「重い・冷たい・溶けるかもしれない」冷凍食品も充実させておきたいところです。冷凍食品に関しては冷凍専用の箱などに入れて配送されるので、実店舗で購入するよりもECサイトで購入する方が、鮮度を保ちやすくなります。保存期限も長く、在庫ロスの低減も見込めるので、積極的に取り入れたい商品といえます。
利便性・操作性の高いサイトを構築する
文字の大きさやボタンの視認性、スムーズにページの遷移ができるか、欲しい商品がすぐに見つかるかといったユーザービリティの高さも購買意欲に影響を与えます。
当然ですが、欲しい商品がなかなか見つからなかったり、エラーが頻発したりするサイトでは、ユーザーは離脱しやすくなります。
サイト構築の際はデザイン性よりも、ユーザーにとっての利便性・操作性を重視するようにしましょう。
定期購入・サブスクリプションを導入する
定期購入やサブスクリプションでリピーターがつけば、安定的に売上を確保できるようになります。そのため、単発利用のユーザーの獲得よりもリピーター獲得のための施策を実施しましょう。
リピーター獲得のための施策としては、定期購入やサブスクリプション以外に、クーポンの発行やメルマガの定期配信、キャンペーンの実施などが考えられます。
集客方法を検討する
ECサイトは開設しただけで利用者が集まるほど甘くありません。利用者を集める方法を検討する必要があります。
集客にはSNSやSEOなどさまざまな方法がありますが、自社ECの場合は、Web広告の出稿が最も集客効果が期待できる施策でしょう。
Web広告のなかでも特に広告配信システムの精度が高いFacebook広告(Meta広告)であれば、小規模事業者でも成果が出すことが可能。購入見込みの高いユーザーに効率的に広告を配信できるため、売上の最大化も狙えます。
物流拠点・システムを整える
鮮度の高い状態での配送を実現するためには、物流拠点・システムの整備が求められます。
ただし、物流拠点やシステムはイチから整える必要はありません。特に大手企業ほど物流量が多くない中小企業においては、既存の外部サービスの利用で事足りるでしょう。自社でイチから構築する手間もコストもかからないうえに、配送業務の効率化も図れるので利用しない手はありません。
※当社2023年10月実績
食品ECの成功事例

最後に食品ECの成功事例を紹介します。カカオ豆の買い付けからチョコレートの製造までを一貫して行なうビーントゥーバー製法の専門店「山奥チョコレート 日和」様では、商圏・販路拡大のためにECサイトを開設。広告運用とマーケティングに精通している会社を探していたところ、株式会社これから に出会います。
営業担当の「どちらも得意です」という言葉を信じてECサイトの制作を依頼。森の中を進んだ先にある実店舗の雰囲気を大切にしつつ、商品を“売る”ための設計を施したECサイトが完成しました。
広告運用の効果も手伝い、ECサイト開設後は売上が10倍にアップ。想定以上の結果が得られたことに、喜びの声を頂戴しています。
まとめ
食品業界のEC化は課題も多く、増加幅も微弱です。しかし、食品業界自体の市場規模は他分野と遜色ないうえに年々拡大しています。これはつまり、現時点における食品ECはブルーオーシャンである、とも捉えられるでしょう。
食品ECを成功させる要素はさまざまなものがありますが、ECサイトの設計や集客方法も食品EC成功の明暗をわける要素となります。株式会社これからでは、ECサイトの制作から集客まで一貫したサポートを行っています。売上ステージにあわせたコンサルにも対応しているので、食品ECにチャレンジする際はぜひ一度ご相談ください。
関連記事
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/17(月)
-
2024/06/14(金)